ブログ
Blog

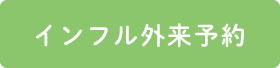


Blog
夏が近づき、気温も湿度も高くなってくると、心配なのが『食中毒』です。特に小さなお子さんは抵抗力が弱いため、大人以上に注意が必要です。今回は、お子さんを食中毒から守るためのポイントと症状がでた際の対応をお話します。
食中毒とは、
飲食物に含まれていた細菌、ウイルス、毒素、有害な物質などを体の中に取り込んでしまった結果、激しい胃腸障害を起こす病気です。
食中毒の原因として考えられるものは次の3つ。ひとつ目は「細菌性(ウイルス性)食中毒」です。細菌(やウイルス)が飲食物と一緒に体に入り直接障害をおこす場合と、食品中で細菌が繁殖してできた毒素により起こる場合があります。
ふたつ目は「自然毒食中毒」。フグや毒キノコ、じゃがいもの芽、ぎんなんなどの自然毒を食べて起こります。3つ目は「化学物質」。農薬や洗剤など有害な化学物質が体の中に入って起こるものです。
食中毒の原因となる細菌やウイルスは、目に見えません。だからこそ、日々のちょっとした心がけが大切になります。
1.つけない:清潔に保つ
食中毒菌は、手や調理器具、食材などを介して広がるので、とにかく「つけない」ことが重要です。
例)腸管出血性大腸菌・カンピロバクター:BBQなどでよく感染する。生肉等を触ったトングや箸で加熱済の食材にも使いまわさないことが重要!
2. ふやさない:適切な温度で管理する
食中毒菌の多くは、20℃~50℃の環境で活発に増殖します。特にお弁当は注意が必要です。生野菜等の食品はできる限り水分を切り、調理した食品はよく冷ましてからお弁当に詰めましょう。また、常温保存の場合、2時間で菌が大量に繁殖するといわれています。
3. やっつける:十分に加熱する
ほとんどの食中毒菌は熱に弱いので、加熱することで菌を死滅させることができます。十分に温めなかった作り置きの食材を口にすることで食中毒になることもあります。
例)サルモネラ菌:鶏肉や卵等の食肉品に存在し、加熱不十分により感染します。
ウェルシュ菌:カレーやお弁当など大量調理された食品で増殖しやすく、温め直しが足りず感染することもあります。大量に調理した食品の作り置き保存の際は温度が下がりやすい浅井保存容器に小分けにする、あら熱をできるだけ早く取る、速やかに冷蔵・冷凍庫にいれることを意識しましょう。
もし食中毒になってしまったら?
もしお子さんが食中毒のような症状(嘔吐、下痢、腹痛、発熱など)を示した場合は、慌てずに以下の対応をとりましょう。
受診の目安は?
以下のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
夜間や休日の場合は、かかりつけ医が休診の場合もあるため、地域の救急医療機関や小児救急電話相談(#8000)などを活用して相談しましょう。
何か心配なことや、お子さんの体調で気になることがあれば、いつでもご相談ください。
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会