ブログ
Blog

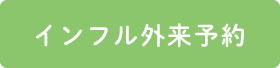


Blog
今年は9月初旬から、すでにインフルエンザA型の発症が各地で報告されています。学級閉鎖になってしまったクラスもあるようです。いつ本格的な流行が始まるか分からない状況ですので、早めの対策が大切です。
今日は「なぜ予防が必要なのか」「インフルエンザの怖さとは?」について、お話ししたいと思います。
🌸インフルエンザとは
インフルエンザウイルスによる感染症で「一般のかぜ症候群」とは分けて考えるべき「小児では特に重くなりやすい」感染症です。
潜伏期間は1~3日。突然の高熱(通常38℃以上)、頭痛、全身の倦怠感、筋肉痛・関節痛などが現れ、続いて咳や鼻水といった上気道炎症状が出てきます。これらの症状は通常1週間程度で回復します。
ただし、小児の場合は中耳炎、熱性けいれん、気管支喘息の悪化などを合併することもあります。
🌸インフルエンザウイルス脳症とは
近年、幼児を中心とした小児において、急激に悪化する急性脳症が増加しています。厚生労働省「インフルエンザ脳炎・脳症の臨床疫学的研究班」による調査では、毎年50~200人のインフルエンザ脳症患者が報告されており、そのうち約10~30%が死亡しています。
入院施設のある病院で働いていると、毎年必ず数人のインフルエンザ脳症のお子さんを経験します。痙攣が長く続いたり、意識障害が残ったり、中には重い後遺症が残るお子さんもいます。
🌸治療は?
抗インフルエンザ薬は熱の持続期間を短くする効果と、早期投与による重症化予防効果があると言われています。特に、幼児や基礎疾患がある、インフルエンザの重症化リスクが高い、呼吸器症状が強いお子さんには投与が考慮されます。原則として、症状出現から48時間以内の使用となります。
一方で、多くは自然軽快する疾患でもあり、抗インフルエンザ薬の投与は必須ではありません。
抗インフルエンザ薬には点滴を含めると全部で5種類あります。年齢や型によってお薬を決めていきます。
| タミフル | ゾフルーザ | リレンザ | イナビル | ラピアクタ | |
| 服用方法 | 5日間の内服 | 1回のみ内服 | 5日間の吸入 | 1日のみ吸入 | 点滴 |
| 1歳未満 |
推奨
|
推奨しない | 推奨しない | 懸濁液は吸入可能。 |
左記4剤が使用困難な場合に考慮
|
| 1~5歳 | 推奨しない | 吸入困難(4歳以下の使用経験はなし。) | 懸濁液は吸入可能。 | ||
| 6~11歳 | B型には考慮 | 吸入可能な場合に限り推奨 | |||
| 12歳以上 | 推奨 | 推奨 | |||
| 呼吸器症状強い時 | 重症例は根拠不十分 | 要注意(重症例には根拠不十分) | |||
🌸なにより大切なのは「予防」!
インフルエンザは毎年流行するし、かかっても薬があるし、ワクチンを打ってもかかってしまうし、、、そのようにお考えの方も多いかもしれません。
しかしインフルエンザは他の風邪と違って高熱で身体への負担も大きく、学校や保育園も長くお休みしなければならなくなります。そして何よりインフルエンザ脳症はたとえ抗インフルエンザ薬を使用していても発症する可能性がある、非常に怖い合併症です。場合によっては亡くなってしまったり、重い後遺症で日常生活すらままならなくなってしまうこともあります。小児科医としてほぼ毎年経験する症例ではありますが、「あのときワクチンを打っていれば結果が違っていたかもしれない」と後悔しているご家族を見るととても辛い思いをします。
マスク、うがい、手洗いももちろん大事ですが、やはり早めの予防接種がお勧めです。
予防接種は全部で2種類あります。
| 注射ワクチン | 経鼻ワクチン
(フルミスト) |
|
| 種類 | 不活化ワクチン | 弱毒生ワクチン |
| 接種方法 | 腕に注射 | 両鼻にスプレー |
| 対象年齢 | 生後6か月以上 | 2歳~18歳 |
| 接種開始 | 13歳未満は2回(2-4週間隔) 13歳以上は1回 |
1回 |
| 副反応 | 発熱、接種部位の腫れ | 鼻汁、倦怠感 |
| 免疫効果発現まで | 約2週間 | 約2週間 |
| 効果持続期間 | 約5-6か月 | 約1年 |
🌸お早めにご予約を!
当院でもすでに9月よりインフルエンザワクチンの予約を開始しています。すでにフルミストはご予約がすべて埋まってしまっている状態ではありますが、キャンセルや在庫に余剰があれば適宜予約枠を開放する予定です。また注射ワクチンに関してはまだ予約に空きがございます。当院ではご家族一緒にワクチンを接種していただける、ワクチン専用外来もありますので、どうぞご利用ください。
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会