ブログ
Blog

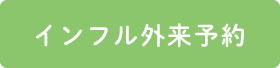


Blog
最近、「発達障害」という言葉を耳にすることが増えましたよね。もしかしたら、「自分もそうかな?」「うちの子はもしかして…?」と気になっている人もいるかもしれません。
今回は、専門医の立場からこの「発達障害」について、**「神経発達症」**という新しい呼び方も含めて、みんなに知ってほしいことをお伝えします。
まず、とっても大切なこと。神経発達症(発達障害)は、脳の働きの特性によるものです。
「親のしつけが悪かったから」「本人が努力しなかったから」といった理由でなるものでは、決してありません!
脳の働きの特性には、いろんなタイプがあります。
たとえば、
などが含まれます。
これらの特性があることで、学校生活や普段の生活で困ったり、友だちとの関係でうまくいかないと感じたりすることがあるかもしれません。
脳に特性があっても、それが生活の中で特に困りごとになっていなければ、神経発達症(発達障害)と診断されることはありません。
「脳の働きの特性があること」と「それによって生活に困りごとが生じていること」の2つがポイントになります。
もし、脳の特性を周りの人に理解してもらえず、「なんでできないの?」「もっとちゃんとしなさい!」と繰り返し注意されたり、責められたりすると、つらい気持ちになってしまうことがあります。
そういったことが原因で、体調を崩したり、ゆううつな気分になったり、学校に行きたくなくなったり、イライラしやすくなったり…といった別の問題が出てくることがあります。これを「二次障害」と呼びます。
二次障害は、本人にとっても、周りの家族にとっても、とてもしんどいものです。だからこそ、周りの人が特性を理解し、その人に合ったサポートをすることが、二次障害を防ぐためにもすごく重要になります。
学校や普段の生活にうまく適応できるかどうかは、周りの環境や、どう育てていくか、そして専門的なサポート(療育など)によって大きく変わると言われています。
私たちが目指すのは、神経発達症(発達障害)のある人が「自分らしさを大切にしながら、毎日を楽しく過ごせること」です。
医療機関での治療は、特性からくる困りごとや、二次障害によって出てきた症状の一部を和らげることを目的としています。
もし、「これってうちの子のことかも?」「もしかして、私って…?」など、気になることや困っていることがあれば、一人で抱え込まずにぜひ相談してくださいね。
専門家と一緒に、より良い方法を見つけていきましょう。
日本精神神経学会(日本語版用語監修), 髙橋三郎ほか監訳, 染矢俊幸ほか訳. DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. 東京, 医学書院, 2023, pp.21-22.
尾崎紀夫・三村 將(監修). 水野 雅文・村井 俊哉・明智 龍男(編集).標準精神医学 第9版.東京,医学書院,2024,pp.256-264.
国立特別支援教育総合研究所. 発達障害と情緒障害の関連と教育的支援に関する研究―二次障害の予防的対応を考えるために― 平成22(2010)年度~23(2011)年度研究成果報告書. 平成24(2012)年3月, p.5, 16, 80, 84.
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会