ブログ
Blog

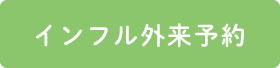


Blog
読み書きの困難(ディスレクシア・ディスグラフィア)について、正しい理解と支援の広がりをめざす啓蒙ブログ「ヨミカキのミカタ」、第2回目は「読み書きの困難を調べる検査」について取り上げます。読み書きサポートラボからの発信です。
第1回「読み書き障害ってなに?」では、読み書き障害(ディスレクシア・ディスグラフィア)に見られやすい特徴のチェックリストを紹介し、該当項目が多い場合や音読の宿題を嫌がる様子がある場合、客観的な評価(読み書き検査)を受けることを勧めました。
実際、どんな検査が使われているのでしょうか?今回は、当法人でも使用している読み書き検査を紹介します。いずれも医師が「検査を受ける必要がある」と判断した場合に受検を勧めています。ご相談内容によっては検査以外の治療を勧めたり、検査を勧めないこともありますので、予めご承知おきください。
・STRAW‐R(ストロー・アール)
読み書きの正確性と流暢性を調べる検査です。ひらがな・カタカナ・漢字をどのくらい正しく読めるのか、どのくらい速く流暢に読めるのか、どのくらい書けるのか、等を調べます。学年平均と比較して困難さを把握します。
対象:小1~高3
時間:小学生 約1時間、中学生 約30分、高校生 約15分(高校生は読みの流暢性課題のみ)
※STRAW-Rは、提携のどんぐり発達クリニックでの実施となります。
・KABC‐Ⅱ(ケィエービーシー・ツー)
対象:2歳6ケ月~18歳11ケ月
時間:年齢により異なりますが、学齢児は2~3時間かかるため、2回に分けて実施されることが多いです。
・URAWSSⅡ(ウラウス・ツー)
読み書きのスピードと代替手段の効果を検証する検査です。読みのスピードが極端に遅いと、文章の内容が理解できません。この検査の「読み課題」では、自力で黙読する課題の他、検査者が読み上げを行う介入課題があり、読み上げの効果があるかを検証できます。「書き課題」では、手書きのスピードと、キーボード入力や使いやすい筆記具等を使った際の書くスピードの違いを見ます。
対象:小1~中3
時間:約30分
※URAWSSⅡは、当院の読み書きに関わる認知能力検査「アセスメントパッケージ」に含まれており、さくらキッズくりにっくでの実施となります。URAWSSⅡ単体では実施していません。
・URAWSS‐English(ウラウス・イングリッシュ)
英単語の読みと綴りの習得度を調べる検査です。「英語の成績だけ極端に悪い」という場合、英語というよりも英単語に躓いているケースが多々あります。英語は音の粒が小さく、表記体系が日本語よりもずっと不透明で難しい言語です。この検査でも、URAWSSⅡと同様に、検査者が英単語を読み上げた場合、その単語の意味が分かるか、綴れなくても音としての表出はできるのかを調べ、音声による補助の効果を検証します。
対象:中1~中3
時間:約20分
※URAWSS‐Englishは、提携のどんぐり発達クリニックでの実施となります。
このように、読み書き検査は複数ありますが、それぞれ測っていることが異なります。医師がお子様の様子をうかがった上で、適切な検査を選択しています。また、学習障害(読み書き障害)は、診断にあたり、知的発達に遅れがないことを確認する必要があります。従いまして、読み書き検査の前に、知能検査(WISC‐Ⅴなど)の受検が必要になることが多いです。
次回の「ヨミカキのミカタ」では、「就学前のサイン」について取り上げます。
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会