ブログ
Blog

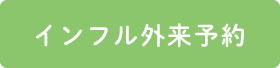


Blog
WISC‐Ⅴ(ウィスク ファイブ)という検査を聞いたことがあるでしょうか?
学齢期のお子さんに大変よく使われている知能検査です。「得意・不得意が分かるから受けてみてはいかがでしょう?」と学校から勧められた方もおられるかもしれません。「発達障害か知りたいのでWISCを受けたい」「不注意や社会性の問題があるのでWISCを受けたい」とおっしゃる方もおられます。ですが、実はこれ、少し誤解があります。今回のブログでは、WISCで分かることや限界についてお話します。
🔸WISCは「発達障害の特定ができる検査」ではない
まず、一般的によく誤解されていますが、WISCは発達障害を見分けたり、特定したりできる検査ではありません。確かに、自閉症スペクトラム、ADHD、LDといった発達障害には、検査結果に特徴的なパターン(プロフィール)が見られることがあります。WISCの結果をグラフにすると、「山や谷」ができるように、得意な部分と苦手な部分の差が表れることがあり、発達障害のあるお子さんでは、その波のかたちに共通点が見られることも少なくありません。
たとえば、自閉症スペクトラムの方では「処理速度が低いことが多い」という傾向が、専門家の間ではよく知られています。しかし、それはあくまでマスデータ(大規模データ)上での傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。実際には、自閉症スペクトラムの診断があっても「処理速度がとても高い」方もいます。
つまり、発達障害には共通する波のパターンが見られることはあるものの、一人ひとりの波の形はそれぞれ異なるということです。
🔸WISCでわかること
WISC‐Ⅴで測定できるのは、知能のうちの一部の能力です。10種類の知能領域のうち、WISC-Ⅴでは5領域を測定しています(言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリー・処理速度)。ここから、本人の強みや、つまずきの原因を把握することができます。例えば、「一斉指示が理解できない」という困りごとがある場合に、その原因は「言葉の理解の弱さか」「聞く力(ワーキングメモリー)の弱さか」といったことを推定します。本人の中での強みがあれば、それを学習方略や指導の手がかりに使ったり、自信につなげたりします。
🔸WISCでわからないこと
WISCは知能検査ですので、知能以外のことは測れません。例えば次のようなことは測定していません。
・性格、行動、多動・衝動性、社会性、感情、運動発達など
また、知能領域でも10種類のうち、以下5つの能力は測定していません。
・読み書き、数量の知識、聴覚処理、反応・判断速度、長期記憶と検索
※「長期記憶と検索」は今後追加されます。
困りごとがあるのに凹凸がなく、平均的なスコアが出る場合、WISCで測定していない領域に困りごとの原因がある可能性もあります。
🔸「スコアが100以上なら安心」ではない
IQや各能力のスコアが平均(100)を超えていても、他の領域よりも低い場合は、そこが苦手な部分であることもあります。本人が強い苦手意識を持っていることもあります。「苦手と言っても平均より高いから大丈夫」と一概には言えません。
WISCは、お子さんの強みとつまずきの原因を把握し、努力の方向性をつかむための材料です。しかし、どんな検査も万能ではありません。「検査のスコアと日常の様子が一致しない」といった違和感がある場合は、医師や心理士等の専門家に質問し、上手に活用できると良いでしょう。
今回のブログはさくらキッズくりにっくの心理士がお届けしました。
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会