ブログ
Blog

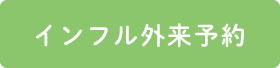


Blog
当くりにっくの読み書きサポートラボより、読み書きの困難(ディスレクシア・ディスグラフィア)について、正しい理解と支援の広がりをめざす啓蒙ブログ「ヨミカキのミカタ」をスタートします。第1回目は「読み書き障害ってなに?」です。
読み書き障害(ディスレクシア、ディスグラフィア)という言葉を聞いたことはありますか?
知的発達や視力・聴力、教育環境に問題が見られないにも関わらず、文字の読み書きに困難を示す障害です。「ディスレクシア」は読むことが困難な状態、「ディスグラフィア」は書くことが困難な状態を表す言葉です。
原因は脳の情報処理の特性にあり、親の育て方や本人の努力不足の問題ではありません。日本ではまだ認知度が低く、「頑張ればできる」と誤解され、支援が遅れることも少なくありません。
「読み書きが困難」と言っても、全く読めない・書けないわけではありません。いつまで経っても音読がたどたどしかったり、漢字がなかなか覚えられなかったりと、読み書きの正確さと流暢さにつまずきが見られるのが特徴です。また、困難さの程度も多様です。ひらがなの読み書きからつまずくタイプ、漢字書字でつまずくタイプ、日本語の読み書きではさほど困難さが目立たず、英語の読み書きでつまずくタイプと、多様な状態像が見られます。
読み書き障害は学習障害の主要型であり、学習障害全体の約8割を占めるとされています。医学的には「限局性学習症」という診断名が使われることが多いです。
具体的には、以下のような特徴がしばしば見られます。
✅耳鼻科で聴力検査をすると正常にもかかわらず、いわれたことばを聞き間違えることが多い。
✅(就学前)文字に興味を示さない
✅(就学後・1年次)音読できなかったり、よく間違えるひらがなが複数ある。
(以下、2年次以降)
✅ひらがなで書けない文字がある。特に拗音や促音が困難である。
※拗音とは(しゃ、ぎゃ、等)、促音とは(小さい「っ」)
✅カタカナが習得できていない
✅音読の速度が遅い
✅読み飛ばしが多い
✅語尾や文末を読み誤ることが多い
✅漢字をなかなか覚えられない。覚えても、忘れやすい。
✅漢字を写字(視写)で、間違える。
✅図形の模写(視写)が、困難である。
✅筆算はできるが暗算が苦手である。
✅九九を唱えることがなかなか覚えられない。
✅ローマ字がなかなか覚えられない。
✅英語の読み書きが苦手である。
※引用:発達性ディスレクシア研究会 「ディスレクシアを理解するために」
さて、お子さんの読み書きに上記のような様子が見られる場合、どうしたら良いでしょう?一般的には、まずは担任の先生に相談することが多いかと思います。もちろん、それは必要なことでしょう。ですが、私達は客観的な評価(読み書き検査)も受けることを強くお勧めします。なぜなら、読み書きの困難は「全く読めない」のではなく、「正確さ」「流暢さ」のつまずきであり、それがどの程度のつまずきなのかは、たとえ専門家であっても主観では大変判別しにくいためです。
次回の「ヨミカキのミカタ」では、「読み書きの困難を調べる検査」について取り上げます。
滋賀医科大学医学部医学科 卒業、大津赤十字病院初期研修医、滋賀医科大学医学部付属病院 小児科、静岡県立こども病院 血液腫瘍科、聖マリアンナ医科大学病院 小児科助教
日本小児科学会 小児科専門医、日本血液学会認定 血液専門医、小児血液・がん学会、日本血栓止血学会